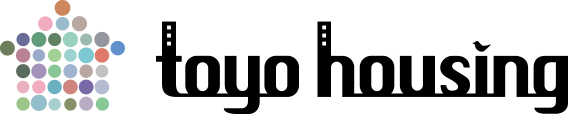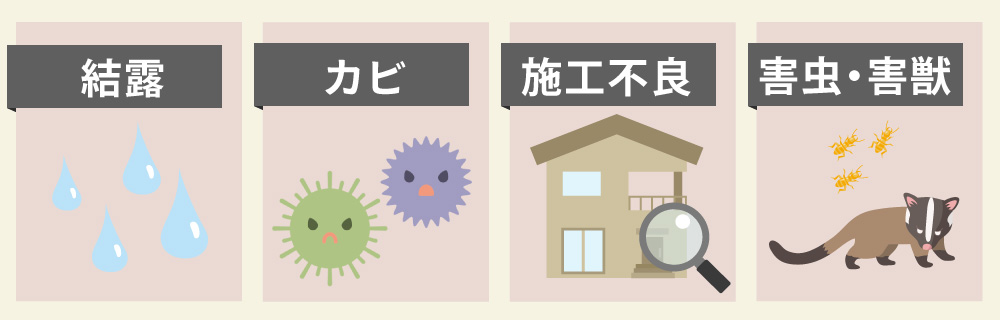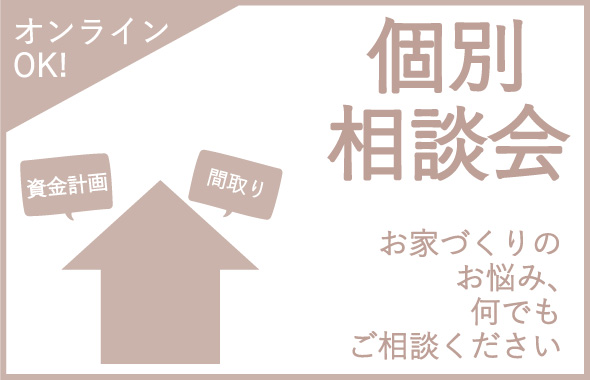注文住宅Q&A
Q&A断熱材は劣化する?劣化の原因や確認・交換の方法を解説


断熱材は住宅の快適性を維持するために重要な役割を果たしていますが、効果が永久に持続するわけではありません。断熱材は使用環境や経年劣化によって徐々に性能が低下するので、適切な対策を講じる必要があります。
当記事では、断熱材が劣化する原因や断熱材の状態を確認する方法などを解説します。住宅の断熱性能を長持ちさせるためのポイントを押さえ、快適な住環境を維持しましょう。
目次
1.断熱材は劣化する?
断熱材とは、熱の伝導を遮るために使われる資材のことです。住宅では天井・壁・床などの内部に断熱材が入っていて、室内と室内との熱の伝達を遅らせたり、温度差による結露を防いだりする役割を担っています。
しかし断熱効果は永久に維持できるわけではありません。断熱材の寿命は建物の状況や環境、使用する断熱材の種類によって異なるものの、30~40年程度で経年劣化して断熱性能が下がるケースがあります。
断熱材の断熱性能が低下すると熱の伝達を遮りにくくなり、住まいの快適性が損なわれます。暮らしやすい住まいを維持するためには、断熱材が劣化する原因を知り、対策を講じることが大切です。
2.断熱材が劣化する原因
断熱材が劣化する原因には断熱材への結露やカビの発生、断熱材の施工不良、害虫・害獣の影響などがあります。
以下では断熱材の主な劣化原因と、原因に応じた対策を解説します。
2-1.結露の発生
断熱材は天井や壁といった構造材の結露を防ぐ役割があるものの、断熱材自体に結露が発生するケースがあります。
そもそも結露とは、水蒸気を多く含んでいる暖かい空気が急激に冷やされ、水蒸気が液体の水に変化することで起こる現象です。住宅の結露には「表面結露」「内部結露」の2種類があり、内部結露が断熱材の劣化につながります。
| 表面結露 | 窓や壁面などに発生する、発見しやすい結露 |
|---|---|
| 内部結露 | 壁の内側や断熱材内部などに発生する、発見しにくい結露 |
結露した断熱材はカビや施工部分からのずり落ちが発生し、高い断熱性能を発揮できません。
断熱材の結露を防ぐには、住宅内部の結露対策を行いましょう。換気をしたり、部屋の中の温度差をなくしたりすると、結露の発生を防ぎやすくなります。
2-2.カビの発生
内部結露などで断熱材が湿気を含むと、カビの発生につながります。断熱材に発生したカビは住宅全体に広がる可能性があり、住宅そのものの劣化にもつながる問題です。
また、カビの胞子は呼吸器系疾患やアレルギーの発症を引き起こすリスクがあります。健康的に過ごせる住まいを維持するために、断熱材にカビが発生しないように対策しましょう。
断熱材へのカビの発生を防ぐには、換気で結露予防を行うことが重要です。結露以外にも、雨漏りや配管からの漏水もカビの発生につながるため、雨漏り・漏水などが起きた場合は早めに修理・点検などを行ってください。
2-3.施工不良
断熱材の劣化は、断熱材の施工不良によって引き起こされるケースも少なくありません。施工不良の断熱材は本来の性能を発揮できず、室外の温度が室内にすぐ伝わったり、構造材の結露が発生したりします。
断熱材の施工不良は作業員の技術・経験不足や、施工時の環境による問題を原因として発生します。「本来入るべき場所に断熱材が入っていない」「断熱材に隙間がある」「極端に湿度が高い環境で施工している」などが断熱材の施工不良の例です。
施工不良を防ぐためには、断熱材について正しい知識を持っていて、信頼できる施工会社に対応を依頼する必要があります。また、住宅の購入前に断熱性能の検査も行うとよいでしょう。
2-4.害虫・害獣の影響
壁の隙間や天井裏などに害虫・害獣が侵入すると、断熱材の劣化につながる可能性があります。
特にシロアリの被害には注意が必要です。断熱材の内部はシロアリが過ごしやすい環境であり、断熱材の中にシロアリが侵入すると住宅木部への食害や、断熱材の劣化を引き起こします。
ただし、住宅の防蟻処理をしっかりと行えばシロアリの被害を予防できます。新築時はもちろん、住宅購入後も定期的に防蟻処理を行いましょう。
また、ネズミやハクビシンといった害獣も断熱材をかじったり、穴を開けたりして劣化させるケースがあります。糞尿によって断熱材の汚損・カビが発生することも問題です。害獣が走り回る音や鳴き声がするといった侵入の兆候がある場合は、早期に専門業者と相談して対策してください。
3.断熱材が劣化しているかどうかの確認方法
断熱材が劣化しているかどうかは、点検口が設置されている場所であれば目視で確認することが可能です。
たとえば天井の断熱材は「屋根裏点検口」、床の断熱材は「床下点検口」を利用して、断熱材の状態を確認できます。
ただし、目視で確認できるのは点検口が設置されている住宅のみです。そもそも壁には点検口がないため、壁の断熱材の状態は目視では確認できません。
また、屋根裏や床下は狭くかつ暗所であり、個人が点検口から入って確認するにはリスクが高い場所です。断熱材が劣化しているかどうかを確実に知るためには、専門家による住宅診断を受けることがおすすめです。専門家は住宅構造を熟知しているので屋根裏や床下を隅々まで確認でき、壁の断熱材についても赤外線カメラなどを用いて断熱欠損の検査を行えます。
4.劣化している断熱材の交換方法
断熱材が劣化している場合は断熱リフォームが有効です。
断熱リフォームには「内断熱工法」と「外断熱工法」の2つがあり、施工費用やデザインへの影響などの点で違いがあります。
最後に、2つの工法についてそれぞれの特徴とメリット・デメリットを解説します。
4-1.内断熱工法
内断熱工法とは、天井裏や壁の内側などの空間に断熱材を入れる工法です。内断熱工法は、住宅建築時の断熱施工や、和室から洋室へのリフォームに合わせた断熱リフォームなどで採用されています。
内断熱工法のメリットは、室内側から行う工事であるため足場を組む必要がないことです。外壁部分をいじる必要がなく、住宅の外観への影響も少なく済みます。
一方で内断熱工法は室内側から断熱材を入れる都合上、壁面を剥がしたり、場合によっては床材も剥がしたりする必要があります。壁面・床材の撤去・交換にコストがかかるほか、家具の移動や一時的な引越しを行わなければならないケースもあります。
4-2.外断熱工法
外断熱工法とは、屋根・外壁・基礎といった住宅の外側部分にボード状の断熱材を貼り増しする工法です。住宅全体を対象とした大規模な断熱リフォームでは、外断熱工法を選択するケースがあります。
外断熱工法は室内側の壁面や床材に手を加えずに済むため、居住者がそのまま生活した状態で断熱リフォームを行える点がメリットです。住宅全体をすっぽりと断熱材で覆うことにより、断熱性能と同時に高い気密性能も得られます。
デメリットとしては、外壁や屋根への断熱材の貼り増しをするために足場を組む必要があり、工事費用が高くなる傾向があります。また、断熱材の貼り増しによって住宅の外観デザインが変わる点にも注意してください。断熱材の厚み分だけ建物が一回り大きくなるので、狭小地や隣地との距離が近い場合などでは採用できない可能性もあります。
まとめ
断熱材の劣化は、結露やカビ、施工不良、害虫・害獣の影響など、さまざまな要因によって進行します。劣化が進むと断熱性能が低下し、住まいの快適性が損なわれるだけでなく、結露による建物の傷みや健康被害のリスクも高まります。
劣化した断熱材は、適切なリフォームによって交換することが可能です。断熱リフォームには「内断熱工法」と「外断熱工法」があり、費用や施工方法に違いがあるため、住宅の状況や予算に応じて選びましょう。適切なメンテナンスと対策を行い、断熱性能を維持することで快適な住環境を保てます。
開催中の見学会・イベント
-
相談会 完全予約制 開催中
2026/02/21 ~ 2026/03/01「間取りで暮らしはラクになる」間取り相談会
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷3-2-9
①9:00/②13:00/③15:00 ※完全予約制
-
相談会 完全予約制 開催中 随時受付中
【土地、資金、間取りの悩みをすべて解決】個別相談会
-
相談会 完全予約制 開催中 随時受付中
【土地の悩みをすべて解決】土地探し相談会